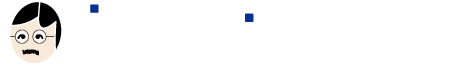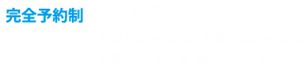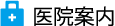「心と社会」44巻1号に掲載

児童精神科医の立場から
はじめに
当院は、愛知県豊橋市にある、思春期デイケアを併設する児童精神科クリニックで開院してちょうど10年になる。初診患者の75%が未成年で、小学生から中学生年代が中心となっている。主訴を挙げると、やはり学校不適応が圧倒的に多い。不適応の内訳では、登校渋りや不登校といった相談が多いが、集団行動がとれないといった学級内の不適応行動が問題になっているケースも少なくない。こうした状況の児童精神科クリニックにとって、学校現場との連携は、子どもの実情に迫るために欠かすことのできない手段である。当院では、数年前から精神保健福祉士の1名を学校コーディネーターとして配置し、学校との連携に力を入れてきた。本稿では、こうした連携を通してみた学校現場のメンタルヘルスについて、その現状と課題について私見を述べる。
「発達障害」というアイテム
受診動機で最も多い学校不適応については、不登校であれ学級内不適応であれ昨今、当院に紹介されてくる際に、学校現場ですでに不適応の背景に発達障害の特性が指摘されていたり、疑われたりする。すべての問題がその特性ゆえ、と言わんばかりの風潮が保育園・幼稚園や学校現場を中心に広がっているのである。10年前開院して間もない頃、発達障害の概念を学校関係者に理解してもらうのにひと苦労したことを思うと、隔世の感がある。なぜ、こんな極端なことになるのか。
学校関係者と連携する中で、子どもの発達や育ちについての認識が、児童精神科医とは決定的に異なっていることに気づかされた。児童精神科医は、個々の生まれ落ちてから(あるいは生まれる前から)の生育史を重視して、その子の資質、その子を取り巻く環境、体験の有り様を吟味しながら、(本来ありうる)育ちを阻害している要因を取り除きじっくり構えて育ちを促そうとする。これに対して、学校現場では、担任教諭は今現在の目の前にいる子どもの姿に注目して、その子の良い点・優れた点を見つけては褒め励まし悪い点・劣っている点を見つけては、手だてを考えみんなに遅れないように背中を押す。与えられた1年という時間枠の中で、与えられた課題を何とか達成したいと考えるのだろう。そこでは、どの子も等しく1年というクロノスの時間が流れる。けれど、どうだろう。我が身を振り返って、学生時代の1年1年がまるで等間隔に流れたようには感じられない。その時間の流れはまったくもって主観的なものである。昔から、子どもの育ちを早生と晩生という言葉で例えることがあるが、子どもひとりひとりが資質も置かれた環境も異なるわけで育ち方が違っていて当然なのである。単純化すると、児童精神科医の考える子どもの育ちは曲線的で不均質であるのに対して、学校現場で想定される育ちは、直線的で均質であるといえる。
学校の先生はやたらと忙しい。会議やら報告書やらで手一杯である。今ここを何とかしなければと考える時、「発達障害」という概念が、手っ取り早く子どもを理解(したような気に)する手近なアイテムになってしまったように思えるのである。そうして、本来吟味すべき資質家庭・学校環境、友人・親・教師との関係性などの雑多な要因を、障害特性という一点に外在化してしまって、子どもの本当の困り感に手が届いていないのが実情である。発達障害と仮に診断がついたとしても、十人十色で、子どもによって困り感は様々であり、また自身は困っていない子も多い。この点は、児童精神科医も反省しなければならない。安易に発達障害概念を広め、発達障害ばかりに衆目を集める片棒を担いだ責任はまぬがれないところである。
発達障害が増えた?
発達障害は果たしてほんとうに増えてきたのだろうか。確かに、学校現場はもちろんのこと臨床の場にしろ、職場にしろ、今はありとあらゆる場所で、発達障害をもつ人もしくは発達障害の疑われる人が増加しているといわれる。増加の原因として、発達障害を「連続体(スペクトラム)」として捉える診断基準の変化、発達障害に関する情報・知識が広く普及したことに伴う社会的な認知度の増大、そして低出生体重児の増加に示されるような胎児環境の変化などが指摘されている。しかし、発見頻度が高まったという認識は衆人の一致するところだが、出現頻度が増加しているという確たる論証は今のところない。あくまで私見だが、社会的な養育環境の変化が深く関わっているのではないかと考えている。すなわち、発達の凸凹を持つ子どもはずっと昔から存在していたはずだが、今ほど目立つことはなかった。これは、地域社会での人々との交わり、大家族的な生活体験、豊富な遊び環境、不便だが工夫のいる生活環境、身の丈にあった目標などに囲まれ、五感を十分に働かせた体験を通じて豊富な生活スキルを獲得して、凸凹をうまくカバーするように発達が促されていったのではないかと推測する。翻って現在の子どもは、地域的なつながりの希薄な環境で、核家族の中、身の丈に合わない過大な目標に振り回され、バーチャルな遊びに逃げ込み、五感を働かせた実生活の体験が乏しく、生活スキルを十分に獲得できぬまま成長している。発達が滞り、凸凹はカバーされることなく露呈されて、発見にいたるのではないかと思うのである。
育ちの失調
ベテラン教師から、健常と思える子どもたちにも発達障害で指摘されるような特性を持つ子が増えているという話をよく聞く。それもまた社会的な養育環境の衰退を物語る証左ではないかと思う。指摘される特性は、相手の気持ちが想像できない、機転が利かない、気持ちが通じ合えないとかそういうことである。この年齢なら当たり前のこと、が通用しないというのである。そして、子どもをよく見ていて勘のいい教師は、発達に凸凹のある子どもへの対応ノウハウが健常とされる子どもの指導にも力を発揮することを理解し実践している。発達障害とかいう以前に、子どもが育っていないのである。
じつは子どもだけの問題ではない。ベテラン教師やスクールカウンセラーとの対話や学校とのケース会議を通じて、中堅から若い教師の中に、子どもの気持ちを想像できない、全体を見通せない、気持ちが通じ合えない面々を発見する。もちろん、教師個々の資質の問題はあり、中には素晴らしい資質の持ち主もおいでだが、30年近く臨床に携わる者
からすると、子どもの気持ちが見えにくい通じ合いにくい先生を見い出すことが以前より明らかに増えている。そして当然ながら親たちも同様なのである。
子どもを見ても、教師や親といった大人を見ても、育てられていないのである。体験に乏しく、自信もなく、しっかり抱えられ支えられることもなく、各々が荒野にたたずんでいるような状況なのである。
こうした育ちの失調を招来している遠因は、やはり日本全体を取り巻く成果主義にあると指摘されることが多い。横並びに、高い達成目標を掲げられて頑張りを強要され、時間との勝負を強いられている世界観である。いつの頃からか、そうした世界観からこぼれる者が続出し、不登校、引きこもり、ニート、貧困と大きな社会問題となっている。人間という動物が快適に過ごせるスピードを遥かに越えてしまっているのだろう。
おわりに
昔はよかったといって、育ちの環境を昔通りに復元することは不可能である。しかし、何が失われて育ちの環境が衰退したのかを十分検討して、失われたものの本質を現代に再生させることはできる。子どもが働ける大人に順次育っていかないと、国力は衰退していく一方になるわけで、育ちの環境を整備することは、国家の存亡に関わる大事である。子どもは
親が育てるのではなく、社会が抱え、支え、育てていかなければならない。
参考文献
1)小倉清: 「子どもの精神科医五○年」論創社、2012
2)牧真吉: 「子どもの育ちをひらく」明石書店、2011