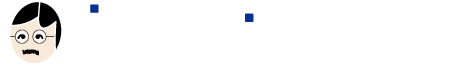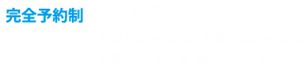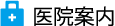「入門 子どもの精神疾患」に掲載
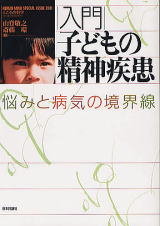
いじめられている?
いじめのようなもの
私のクリニックを訪れる子どもやその親から、それこそ報道で取り上げられるような凄惨ないじめを被ったという話は、開業九年目となるが聞いたことがないそうしたケースはいろんな点で複雑な要因が絡まり、精神科を利用するという手段が状況にそぐわないか、あるいはすでに医療という範疇を越えているか、いずれにしろ市中の児童精神科クリニックを受診することがないのだろう。では、いじめが少ないのかと言えばそんなことはない。日々の臨床のなかで、「いじめ」という言葉を聞かない日はない。障害の別に関わりなくである。
母親はこんな風に切り出す。
「……息子が言うには、どうもいじめのようなものに遭っているようで……」
あるいは―。
「……娘はいじめみたいなものがきっかけで……」
どうにも歯切れが悪い。いじめと断じず、「いじめのようなもの」とか「いじめみたいなもの」と最近は表現されることが多い。担任に尋ねたり、同級生の親にそれとなく聞いたりしても、いじめの実態がつかめない。けれど、我が子は○○にいじめられたと断固主張しているのである。
考えてみれば、いじめもどこまでが遊びやたわいのない冗談であるのか、きっちり線引きするのはむずかしい。悪意が込められたかどうか、あるいは悪意を感ずるかどうかを決するのは、微妙な判断である。また、見ている立ち位置で見え方が違ってくるのは、いじめ事象に限らず万事に共通する道理である。いじめを客観的に見ていこうとすると、だんだん訳が分からなくなってくる。いじめがあると言えばあるし、ないと言えばない、というように。しかし、ここで大事なのは、子どもがいじめられていると言うならば、それはその通りなのであって、子どもは「いじめのようなもの」を現在体験しているのである。また、担任教師や同級生がいじめといえるような事実は見当たらないと言えば、それもその通りなのである。双方の話を先入見なしに拝聴すると、どちらにも嘘はないと映ることが多い。この乖離をどう理解し受け止めていくかがポイントである。
本稿では、いくつかの症例を取り上げながら、子どもたちが訴えるいじめ体験をどのように理解し、どう受け止めていくかについて述べる。このテーマに限っては、どこまでが悩みで、どこからが病気かという議論は、意味がないように思う。後述するが、いじめは重かろうが軽かろうがその時点できちんとした対応をしておかないと、後々困ったことになるのである。また、編集部から与えられたテーマは学童期のいじめであるが、学童期にとどまらない論調になってしまうこともお断りしておく。
症例A子(中学2年生)
小学校中学年までは人なつこくて元気な子と言われていた。しかし、五年生になって気の強い級友に嫌われ「あの子としゃべるな」と周囲に圧力をかけられ、クラス中の女児から無視されるようになったという。登校を渋りがちになったが、まもなく学年が変わってクラス替えとなり、仲のよかった子とクラスが一緒になって、以降いじめは収まり、登校も順調だった。ところが、中学二年生になり、五年生の時にいじめてきた件の女生徒とクラスが一緒になった。四月の中旬から登校を渋り出し、母親に車で送られて何とか登校するものの、教室には入れず保健室で過ごすようになった。養護教諭の勧めで当院を受診した。
A子の話では、問題の級友は自分をまるで無視していて、時々ひそひそ周りの級友と自分の悪口を言って笑っているという。母親はA子の話を信じており、教頭と担任教師にいじめを解決するように詰め寄ったが、曖昧な態度に終始する学校の対応に憤慨していた。養護教諭から届いた情報提供書には、いじめのことよりも、対人スキルの不足や状況の読めなさ、授業での教科による集中のムラなどの軽度発達障害的な特徴が列挙されていた。当人側と学校側との間に明らかな認識の相違があるので、本人と母親の了解を得て、学校と連絡を取ることにした。学校との連携を担当する精神保健福祉士(以下、当院コーディネーター)が養護教諭から得た情報では、A子が名指しした女生徒はA子について良きにつけ悪しきにつけまるで関心がないようであり、周辺への調査でも無視や悪口の流布を含めいじめの事実は確認できないという。むしろ、A子の話を鵜呑みにして学校に乗り込んできた母親の尋常でない剣幕が話題になったらしい。
結局のところ、事実は謎である。憶測すれば、五年生当時のトラウマがフラッシュバックしてきて、ないものがあたかもあるかのように見えてしまう「独り相撲」をA子がとっているのではないかと解せる。しかし、A子がいじめられていると言う時、それはA子にとっては内的真実である。また、件の女生徒がいじめるまでにも至らずA子には関心がないと言う時、それもまた当人にとっては内的真実なのだろう。私は、目の前に座ったA子が〝いじめのようなもの〟に遭遇してどうにも参っており、それを見るに見かねた母親が気丈にも娘のために孤軍奮闘しているという具合に、A子親子を見ていくことにした。そこで、母親同意のもとに養護教諭と担任教師に来院を要請し、当院コーディネーターを交えて話し合いを持った。
A子には確かに発達上の特性が認められ、事実認識が歪んだ形になりやすい。いじめの事実がないという学校の見解は十分納得がいくものだが、現在はいじめられた心性でいっぱいになっているA子に、いじめはないという事実を突きつけても堂々巡りになってしまう。これは母親に関しても同様である。などと説明し、いじめのようなものを受けているとするA子の見解に寄り添う治療スタンスについて理解を求めた。
その後、A子は徐々にいじめの話題から離れ、自分の得意なアニメや絵の話、教室には入れないが美術部には顔が出せ、そこには相談にのってくれる信用できる先輩がいること、将来の夢などを語るようになった。それとともに、保健室登校から徐々に教室に顔を出すようになり、教室に登校できるようになっていった。
A子にとっても母親にとっても、不安におののいている存在を何も聞かずに受け入れてくれる場所が必要だったのだろう。また、心底に押し込めていた学童期のいじめ体験を表に出し、辛かった五年生の自分をきちんと慰めてもらう必要があったのだろう。
この症例では、過去のいじめ体験が現在に蘇り、いじめのようなものを幻出させたのであるが、次の症例でも過去と現在が交錯している。
症例B子(中学1年生)
いじめのようなもの B子は元来物怖じしない、正義感の強い子だった。小学校五年生の時、先生の指示に従わずむしろ反発して周りに八つ当たりするような女児と同級になった。B子は黙っていられず、その子に面と向かってみんなに当たり散らすのはやめるように注意したという。すると問題の子は、B子を標的にして嫌がらせをするようになった。教科書やノートに落書きをする、上履きを隠す、机や椅子の脚を通り際に蹴るなどの執拗な嫌がらせを繰り返した。B子から事の次第を聞いた母親は早速担任教師に確認を求めた。若い男性教師は事実関係を調べて対応すると約束したが、その後一向に進展する気配がなかった。業を煮やした母親が学年主任や教頭に話を上げたが、対応はしどろもどろだった。他の父兄の話では、低学年の頃から問題の子の父親は学校から指摘があると逆に開き直り、担任の不手際だといって校長室に怒鳴り込んでくるという。そうした経緯があってか、学校側の姿勢は曖昧で、六年生は絶対同じクラスにしないというのが精一杯の対応のようだった。それでもB子は頑張って登校を続けた。
中学に入学し、B子は学級委員長に立候補して選ばれた。いくつかの小学校から上がってくる中学なので初顔も多いのだが、B子は自分の信念に従って、クラスのルールを守ろうとしない生徒に対しことごとく注意して回った。まもなくクラス全体からB子のやり方に非難が集中した。担任教師からもB子に注意がなされた。B子は「クラスのために正しいことをやっているのに非難される。かばってくれてもいいはずの教師さえも私を非難する」と言って、突然登校しなくなった。母親は正しい行いが認められないばかりか、教師が率先して非難するとは何事かと学校側に詰め寄ったが、話し合いは平行線だった。B子は「生きていても意味がない、消えたい」などと漏らし、「非難してくるみんなの目がこわい」と言って外出を拒むようになった。母親の相談を受けていたスクールカウンセラーからの紹介で当院受診となった。
B子は意気消沈しながら、「みんなして私をいじめる。生徒も先生も誰も信じられない」と語り、「何もかもうまくいかなくなったのはあいつのせいだ」と小学校五年生の時に嫌がらせをしてきた女生徒を名指しで罵った。学校には金輪際行かないと宣言した。
その後、心理療法士によるカウンセリングへ導入したが、そこで、B子には常識よりも厳格な自分流の正義の念があり、他者の意見をまるで受けつけない頑固さが浮き彫りとなった。一方、母親了解の下に当院コーディネーターが担任教師から得た情報によれば、B子のクラスメイトへの注意・指導は細かく執拗で常軌を逸しており、相手の感情がまるで見えていないようだった、という。
結局、B子は中学卒業まで中学の代わりに当院デイケアに通った。
B子の話では、中学での出来事を思い出すと小学校五年生当時の光景が鮮やかに浮かび上がり、いつの間にか憎い女生徒の顔だけになってしまうのだという。中学での出来事はいじめとは言いがたいものだが、タイムスリップ現象によって小学校時代のいじめ体験と混交し、B子の中で陰惨ないじめ状況と映ってしまったのである。私たちはB子のいじめのような体験を傾聴しながら、安心して過ごせるデイケアという居場所を提供し、デイケア・スタッフやメンバーに心を開くのを待った。次第に年上の女性メンバーに甘えるような仕草が見られるようになった。心理療法士は、こんがらがった糸をほぐすように、混交した過去と現在の体験を区分けし再構成することを促していった。クラスの中で自分の勘違いや行き過ぎがあったのではないかと考えるようになった。それとともにB子は少しずつ自分の特性に目を向けるようになっていった。三年生になると、学校にも時々顔を出すようになった。
中学での出来事はクラス中を巻き込んだ騒動になってしまったが、A子と同様にB子の場合も、学童期のいじめ体験が燻っており、それが現在を歪んだ形に見せてしまったのである。
ところで、B子は高校を卒業する時期になっても五年生の時のいじめ相手を深く恨んでおり、変わらぬ憎しみを語った。こうした遠い過去のいじめ体験を、まるで昨日のことのように語る青年たちが時々クリニックを訪れる。その口吻は過激で、曰く「見つけ出してぶん殴ってやる」、曰く「殺したい」など、新聞紙上を賑わす事件に発展するのではと危惧する勢いなのである。彼らは入力情報を偏った見方で解釈し、偏った反応を示す。基底に発達の凸凹が存在していると考えられるケースが多い。タイムスリップ現象によって、嫌な体験が芋づる式に次々引き出されて集積し、その集積の上に表象として対人関係の原初的な幻滅であるいじめ体験が君臨しているようにみえる。その他のポジティブな思い出ははじめからなかったかのようにすっかり凌駕されてしまっているのである。こうした体験様式は不幸としか言いようがない。事実は不明だが、大概そのいじめのような体験は教師や親にうまく汲み取ってもらえなかったか、伝わっても納得いく対応がなされなかったと述懐される。子どもがいじめられていると言う時、事実関係がどうあれ、解決より何より、子どもを受け止め大丈夫であると保証することが大事であろう。そうすることで、後に不幸な体験様式が作動するのを減じることができるかもしれない。
次の症例は、前の二つのケースと趣きが異なる。
症例C男(中学2年生)
幼児期に表情が乏しく言葉の遅れがあるということで、専門病院の発達外来で「自閉傾向あり」と指摘され、言語療法を三、四年受けた。就学に際して言葉も発達し知能的にも平均に届いたと言われ、通常学級へ入学した。しかし、場の状況や流れを察知することが苦手で、何事もワンテンポずれるため、教師や世話好きなクラスメイトから注意されることが再々だった。三年生になると、からかいやちょっかいを受けるようになり、泣いて帰宅することもあった。自信がないと見てとった母親は、C男に柔道を習わせることにした。C男は柔道が気に入り、稽古に熱心に取り組んだ。高学年になると頭角を現し、公式試合で上位に入るようになった。
中学に入ると、他の小学校から来た特定の生徒たちに早くから目をつけられ、からかわれたり、パシリをさせられたりするようになった。その中学には柔道部がなく、やむなく陸上部に入部したのだが、そこでも上級生たちから馬鹿にされ、無視されるようになった。しかし、こうしたいじめについて、C男本人はいっさい誰にも話さなかった。そればかりか、C男の行動を不審に感じた教師からいろいろ尋ねられても見え透いた嘘ばかり返答するので、教師からも信用されなくなっていった。いじめの実態を知ったのは母親が最初だった。小学校が同じ子が見るに見かねてその親に打ち明け、C男の母親に情報がもたらされたのである。当初、学校は母親の話をまったく信じなかったようで、周辺の聞き取り調査をしてやっと事態を認め、謝罪したのである。C男は、具体的ないじめ事実について確認すれば認めるが、自分から話し出すことはなかったそうである。結局、C男の両親は転校を申し出た。C男が休日に通う柔道場の道場主に、柔道部のある学校へ移った方がいいと助言され、母親が積極的に教育委員会に掛け合って実現させたのである。
二年生に進級時、C男は近隣の柔道部のある中学に転校した。何がある訳ではなかったが、転校先の養護教諭からの紹介で当院を受診した。紹介書には「デリケートな子なので、今後の指導について連携をお願いしたい」と記されていた。C男は本人は気づいていないが、とぼけた味のある子で、不器用でまっすぐ過ぎる芯を持っていた。いじめについて尋ねると、「あんまり言うと卑怯な気がした」と武道家然とした答えが返ってきて、これまでのことが腑に落ちた気がした。母親はC男のいじめ体験の傷つきを心配していたが、私には柔道部に入ってイキイキしているC男が頼もしく見えた。
新しい中学、とりわけ柔道部では、C男の泰然とした自分の世界が顧問からも部員からも受け入れられ、その実力と相まって一目置かれる存在となったようである。
C男にはいじめ体験があまり堪えていないように見えた。嫌なことは忘れる、覚えていないと語るがごとく、C男は根っからのポジティブ思考の持主であり、そうやって幼児期から自分を守るすべを身につけてきたのだろう。
このケースでは、さらに別の要因が絡んでいた。初診時C男の泰然とした様子と母親の強い不安が奇妙なコントラストを形作っていたが、その違和感の理由は以後の診察の中で次第に明らかとなった。母親自身が、小学校から中学校にかけていじめを体験し、泣く泣く登校していたのだという。当時いじめから逃れるため別の学校に移ることを親に懇願していたが、転校は許されなかった。C男が中学に入っていじめられていると知った時、転校という二文字が真っ先に浮かんだという。遠い昔の自分とC男が重なって、昔の自分につき動かされるようにC男の処遇を決めていったのだと思われる。
このように、親自身が学校時代いじめを経験しているというケースは珍しくはない。そんな時、いじめ状況の把握や学校の姿勢・対応をめぐって、自身のいじめ体験が投影されることが少なくない。妙に歪んだ理解の仕方をしたり、何でもないと思える一言に過剰な反応を示したりする。いじめをめぐって親とやりとりする際に、親自身のいじめ体験についても留意しておく必要がある。
医療機関にできること
いじめ問題について、医療機関ができることは限られているかもしれない。そもそもいじめが理由で受診してくることはなく、子どもは学校不適応や集団不適応、あるいは身体症状を主訴にわれわれのもとに連れてこられる。そして、不適応の原因として、いじめやいじめのようなものが差し出されてくるわけである。いじめられていると訴える子どもの言い分を傾聴して、その思いを受け止め、安心できる環境を提供するというのがわれわれの最大の役目である。しかし、いじめ(のような)状況は、善悪二項対立のような単純なものではないので、その状況をできるだけ正確に把握するため、親や教師から十分な聴取を行う必要がある。私のクリニックでは、コーディネーターが場合によっては学校へ出向いて、担当教諭や養護教諭と面談し、学校内の微妙な空気感までも拾ってくる。子どもの言い分、親の言い分、学校の言い分はたいてい少しずつ食い違っていることが多く、ときには正反対だったりする。そのために親と学校が反目していることもある。この食い違いや乖離をどちらかにへんに加担することなくそのままの形で、言うならば立体的に、子どもや親、学校に示しながら、子どものために親や学校に出来ることを探っていくというのもわれわれの立場でできる重要な役目と考える。
おわりに
いじめには二つの側面がある。いじめられている側と、いじめている側である。前に述べたように、いじめられている子どもと、いじめている子どもの言い分が符合することはまれであり、事実関係は薮の中であることが多い。したがって、いじめられていると訴える子どもに出会うとき、私たちがまずなすべきことは、いじめ状況を解明することではない。子どものいじめられている気持を受け止め、子どもをそのまま受け入れることである。いじめられていると感じるとき、その軽重を推し量る余裕は子どもにはない。そんないじめの内にも入らないようなことで、などと言ってはいけない。「そうか、それで君はいじめられた気がしたんだね」と子どもの気持を受け止め、必要ならば時間をかけて誤解や曲解を解いたり、認知の修正を試みたりする。また、C男のケースで示したように、子どもと同様に親の気持にも配慮を要する場合がある。
小学校低学年で、いじめ状況が分かりやすく見えるケースでも、いじめたとされる側が、いじめられたとされる側に謝罪すればすむというものでもない。多くはそんな形で処理されがちだが、いじめたとされた側の言い分もしっかり受け止めた上で謝罪という段階に進まないと、
後々タイムスリップ現象の種になる遺恨を残すことになるのである。
杉山登志郎が提唱したタイムスリップ現象は、広汎性発達障害に見られる独自の記憶の病理とされるが、発達障害と診断のつかない軽い発達の凸凹を有する者にも広く認められる。いじめ問題を考えるとき、常にその現象の関与を念頭に置いておく必要がある。