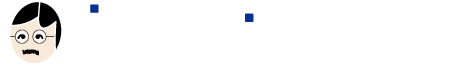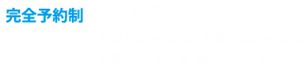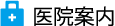思春期青年期の食行動異常
1.摂食障害とは
思春期における食行動の異常といえば、拒食と過食である。例えば、ダイエットややけ食いの延長上で、そうした状態が定着すると、摂食障害(Eating disorder)と呼ばれる病態となる。むろん、ダイエットだけが原因ではなく、その理由や背景はさまざまである。現代のようにダイエットブームではない19世紀にも「摂食障害」の症例は存在したのである。この障害は、米国精神医学会の精神疾患の診断統計マニュアル(DSM-Ⅳ-TR)では、表1に示したように3つ(下位分類を含めると5つ)に分類されている。臨床的に重要なのは、拒食症(無食欲症)と過食症(大食症)である。筆者が精神科医となった1980年代半ばには、拒食症と過食症の割合は拮抗していたが、近年では圧倒的に過食症の割合が増加(拒食症の約2倍)した。また、患者数は最近の20年間で約10倍に増加したともいわれ、社会問題化してきている。男子は少なく(5%以下)、診療に訪れるのはほとんど女子である。
表1 摂食障害の分類(DSM-Ⅳ-TR)
1.神経性無食欲症(Anorexia nervosa)
1)制限型(Restricting type)
2)むちゃ喰い/排出型(Binge eating/Purging type)
2.神経性大食症(Bulimia nervosa)
1)排出型(Purging type)
2)非排出型(Non-purging type)
3.特定不能の摂食障害(Eating disorder not otherwise specified)
拒食症は、標準体重の85%以下のやせがつづいて、無月経が起こってくる。心労などによる食欲不振とは異なり、いくつかの病的な特徴が認められる。約半数の患者がダイエットをきっかけにやせていくが、目標体重を過ぎても、体重をさらに減らすことにこだわりつづける(やせ願望)。自分のやせを認めようとはせず(否認)、むしろ太っているとさえ考えている(身体イメージの歪み)。ダイエットの有無にかかわらず、体重増加を極端に怖がり(肥満恐怖)、食事そのものを嫌悪するようになる。その一方で、飢餓の反動により、料理や食物に強い関心を向け執着するといった矛盾がみられる。また、やせているにもかかわらず、何かしていないと落ち着かない様子で勉強や運動に熱中する(過活動)。しかし、長続きせず徐々に対人関係が疎遠となり、活動は停滞する。表1に挙げたように拒食症には、少食によってやせを維持する制限型と、飢餓の反動で過食するようになり、やせを維持するために排出行動(1)を行うむちゃ食い/排出型がある。
過食症は、短時間に大量の食物を衝動的に食べる発作を繰り返す病態である。いったんむちゃ喰いがはじまると、自分の抑制が利かず食べることが止められない。何千キロカロリーもの食品を、しかも日頃は敬遠しがちな甘く脂っこい食品を短時間で食べ尽くしてしまう。過食後は後悔や自責の念にさいなまれ、居たたまれない気分に陥る。ここで排出行動をとるか否かで排出型と非排出型に分けられる。体重は標準体重の85%以上である。
拒食と過食は一見まったく反対方向の行動と映るが、時期によって拒食から過食へ(あるいは逆へ)変化したり、また制限型からむちゃ喰い/排出型へ移行したりすることが多い。また、やせ願望や太ることへの異常なまでの恐怖心が共通して根底にあり、片や空腹感が分からず、片や満腹感が分からずという、食をめぐって表裏一体の関係にある。
(1).自己誘発性の嘔吐または下剤、利尿剤や浣腸の乱用によって、内容物を速やかに体外に排出しようとする行動。英語では‘purging’といい、浄化・浄罪を意味するとともに、下剤をかけるという意味がある。
2. 摂食障害における心身の特徴
1)身体的な特徴
摂食障害によって生じることの多い身体症状を表2に掲げた。拒食症の身体症状は栄養失調に基づくものである。体重減少が進むと、脱水や電解質異常が生じ、不整脈が出現しやすくなる。さらに進むと、腎機能低下や心機能低下をきたし、死に至ることもある。これらの症状は体重が戻るとともに改善を示すが、成長期に栄養不良がつづいた場合、低身長となることがある。過食症の場合、体重が正常範囲にあり栄養状態に問題がないため、異常を認めないことが多い。しかし、排出行動が長期にわたると、電解質が失われ、体液のバランスを崩したり、腎機能や心機能の低下をきたすことがある。また、過食・嘔吐が続くケースでは、拒食症の場合でも、唾液腺(耳下腺・顎下腺)の腫脹、歯牙酸蝕症(2)、齲歯、吐きダコ(3)がみられる。骨の輪郭が浮き出るほどのやせでも、唾液腺の腫脹によってエラが張った特有の顔貌を呈する。
(2).歯のエナメル質表面の脱灰症。通常はメッキ工場などの酸性蒸気を吸う職場環境などで働く人の職業病として認識されているが、摂食障害者の場合、頻繁な嘔吐によって逆流した胃酸が歯牙を溶かす。
(3).のどに指を入れて吐くため、歯の当たる右手背の第1指、第2指の付け根に胼胝が認められることが多い。
表2 摂食障害による身体症状
拒食症
身体所見:低血圧、徐脈、冷え性、低体温、皮膚の乾燥、うぶ毛の増加
便秘、浮腫、カロチン症(皮膚の黄染)、抜け毛等
血液検査所見:肝機能障害、白血球減少、貧血、コレステロール値異常
電解質異常(低ナトリウム、低カリウム血症)など
内分泌異常:無月経(女性ホルモン低下)、低身長(成長ホルモン低下)
重篤な障害:低血糖性昏睡、脱水、腎不全、不整脈、心不全、骨粗鬆症、結核の合併など
過食症
身体所見:唾液腺の腫脹、歯牙酸蝕症、齲歯、吐きダコなど
血液検査所見:電解質異常、腎機能障害など
2)心理的な特徴
先に述べたように、拒食と過食は表裏一体の関係にあるので、合わせて述べるのが適切と思われるが、ここでは理解しやすいように両者を分けて述べることにする。
a)拒食の意味と利点
摂食障害は、まず拒食からはじまると考えてよい。20年以上前には、胃の調子が悪いとか、食べると気持悪くなるといった理由で無食欲(anorexia)を訴える患者が多かった。実はこの形が拒食症の古典的な原型である。今日ではあまり見かけなくなり、わずかに小学生までの発症ケースでみられる。このタイプでは、「成熟に対する拒否」(4)、「幼児期へのあこがれ」といった心理機制が指摘されている。
今日多いのは、前述したようにダイエットをきっかけに拒食に至るケースである。減量をめざした理由を患者に尋ねると、体形について知人や級友から何か指摘されたとか、美しくなりたい、俊敏になりたいとかいった答えが返ってくる。これらはいずれも他者の評価を意識するものであり、自分の存在感を集団の中で、また自分自身の中で高めたいという願いにほかならない。彼女らはなにゆえに自己存在感を求めるのか。拒食に向かう背景として、挫折や敗北体験が挙げられる。勉強、部活動、友人関係などで自分の優位性を保てないと感じる体験を経て、拒食に至る。彼女たちは元来強迫的で、完全主義的な性格の持ち主であるとともに、自己愛的な高い達成欲求をもつ人々である。そのような人間にとって、挫折や敗北は耐えがたい体験である。下坂1)は、拒食の意味を「自己存在の証し」と指摘し、「挫折体験を希薄化させると同時に、自己をコントロールすることができるという力感・達成感と身体的な存在感覚の強化とに裏打ちされた『かりそめの自分らしさ』の樹立」であると述べている。彼女たちは、絶えず食品のカロリーをチェックし、日に何度も体重計に乗り、鏡でやせ具合を確認する。食べると太るという強い信念(肥満恐怖)があり、飢餓感を押さえこみ、自己を統制することに全身全霊を傾けている。身体を賭けた自己存在の証明である。やせを達成していく自分に自己存在感を感じて、自己愛的な満足を得ているのである。彼女たちの自己愛は、人並みであることを嫌悪し、人とは違っていたいという心性(「平凡恐怖」2))にも反映している。度を超したやせという現実を受け入れず、躁的防衛(5)で「大丈夫」と言い張り、過剰適応的に行動する。また、拒食をめぐって家族の関心を一身に集め、家族の中で確実に存在感が増大してくる。やせ衰えた身体の持主ということで役割や責任が大幅に免除され、手厚く配慮されることになる。家族を巻き込み、親を思い通りに操ることができるのである。こうした意味や利点を持つ症状を彼女たちは簡単に手放すことはできない。
(4).体の成熟や女性性を嫌悪したり拒否したりする心性をさすが、フェニミズムの文脈では、摂食障害を女らしさの文化規定から逃れて、女性が自分自身の自律性を保つための行為と規定している。
(5). 抑うつ的不安,罪悪感,そして喪失感から自我を保護するために、その現実を否認し、現実を万能的に解釈しようとする心的機制。
事例A 中学生女子 13歳
A子は幼児期よりしっかりしていて、手のかからない子であった。小学校では教師から色々な場面で模範的であると評価されていた。中学に入学し、バスケットボール部に入部した。少しぽっちゃりした体形であったが、部活の上級生から「もう少しすばやく動けない?」と注意されたのをきっかけにA子はダイエットを決心した。みるみる体重は減ったが、イライラして怒りっぽくなった。母親の作る食事に難癖をつけ、調理方法に口出しするようになった。また、自分の食事(ご飯2口に野菜の煮物少々)を秤にかけて重さを測り、その数値を母親に確認させたり、母親や弟の食事に口をはさみ、あれとこれを食べろと指示したりするようになった。標準体重の-25%程度になっても、部活の早朝練習に率先して参加したり、学習塾へも積極的に通った。両親に説得される形で、やっとのことでクリニックを受診した。A子は最初困ることはないと言い切った。身体について聞いていくと、ガリガリの体を指して下腹と太股がまだ太いと述べた。そのうち、太ることがこわいと語り、次第に少し疲れやすいと告白した。
この後、A子は回復に向かっていくが、その過程で、「やせていたい自分」と「健康になりたい自分」が彼女の心の中で常に闘っていた。最初は圧倒的にやせを求める自分が大きかったが、徐々に健康を求める自分が育っていった。A子はしばしば回復の不安を語り、抑うつ的となった。回復すると、みんなが離れてしまう、見捨てられてしまうといった自立をめぐる不安である。回復してもなお家族や治療スタッフから支援されるということが信じられるようになると、健康を求める自分が大きくなっていった。
b)過食の意味と利点
過食は、拒食の挫折であり、拒食で押さえこんでいた飢餓感の猛烈な解放である。食べることの自己コントロールを手放したが、自分の中にあふれる不安や緊張を刹那的に過食が緩和してくれることを知るのである。また、強い肥満恐怖に応えるように、自己誘発性の嘔吐や下剤の乱用が過食による体重増加を抑制し、拒食の代替となって機能するようになる。過食・嘔吐や下剤の乱用は、口腔から咽頭、食道、胃、大腸、肛門に至る身体感覚を増大させ、自己存在感を高めるのである。すなわち、過食もまた、拒食と同様に、身体を賭けた自己存在の証明という意味がある。さらに、過食から嘔吐に至る一連の行為が強烈なストレス解消法であるとともに、麻薬のような密やかな快楽となっているのである。
事例B子 高校生女子 17歳
B子は元来負けず嫌いで、勝ち気な性格であった。女子高に入学後、ダイエットをきっかけに拒食となったが、すぐに過食に転じた。毎夜、夕食を普通に食べた後、余っているご飯やおかずを平らげ、さらに冷凍庫のピザやグラタンを温めて食べ、最後に学校帰りに買っておいた菓子パンを何個か詰めこむのである。B子は、食べている間は無心になれる、何も考えなくていいしホッとできると言う。しかし、いよいよ食べ尽くす頃になると、やるせない気分がみるみる胸いっぱいにこみあげてくる。急いで、B子は風呂に入る。彼女の場合、風呂場のシャワーで音を消して、思う存分ビニールのゴミ袋に吐き出すのである。トイレでは家族に怪しまれるし、またどれだけ吐けたのか確認がしにくいと言うのである。思った通りに吐けたときにはスッキリするし、「よし!」という気になるのだと言う。じつは、B子は授業中に、夜の過食に備えて何を帰りに買っていこうかとウキウキした気分で思い描いていると告白した。しかし、B子は急にどうにも切ない気分が襲ってきて、何もかもが嫌になって死にたくなることがあるとも語った。
このように、過食・嘔吐には秘事を愉しむ気配が強い。これは性的なニュアンスを含むものであり、口腔を通した自慰行為と捉える見方もある。一方で、先に述べたように、過食が拒食を貫き通そうとした意思の挫折であるため、抑うつ感や絶望感をもつことが多い。拒食では徹底されていた自己規律(強迫のしばり)が保てなくなり、心のあちこちにゆるみの出た状態である。そのため、衝動の抑制が利かず、自傷行為や大量服薬といった行動化や性的な行動化をしばしば認める。
さて、B子の場合も治療経過の中で、「治りたい自分」と「治りたくない自分」が心の中にあることが明らかとなった。治りたくない自分は圧倒的に大きく、刺激的なストレス解消法を失いたくないし、密やかな快楽を捨て去れないと言うのである。一方、治りたい自分は最初のうち観念的で頼りない存在であった。治りたい自分が日常の何げない問題に向き合って処理できたりするようになるにつれ、わずかずつ存在感を増していった。長い治療経過の中で、紆余曲折を経ながら、治りたい自分が自信をつけてふくらみ、B子の過食・嘔吐の回数は減りつづけて、人間関係の大幅な改善がみられた。
3.看護の役割
摂食障害の者たちは、これまで述べてきたように、家族の中であるいは学校の中で、身体を賭けて自己存在感を強く求めている人たちである。裏を返すと、摂食障害を発症するまでの間に、自分という存在に確かな手応えを感じていなかったということになる。こんなふうな自分を、家族や友人たち、まわりの人間が抱えてくれていて、それでいいよと保証してくれているといった安心感がないのである。彼女たちは、人を信じることができず、甘えることの下手な人たちである。治療に関わる際には、この甘えをめぐる問題が生じてくることに留意しておく必要がある。もう一つの留意点は、彼女たちの心の中に、「治りたい自分」と「治りたくない自分」が存在しているということである。治したいと宣言して入院したものの、病棟内でやることは治りたくないような行動ばかりという事態が往々にして起こる。そのとき、問題行動ばかりに目を向けて対応すると理解し合える機会を失ってしまう。彼女たちは人を信じられないが、心の底では人を信じたいのである。誰にも分かりっこないと思いながら、分かってほしいのである。治りたいが、治りたくないという矛盾した気持をその都度汲みながら寄り添っていくと、次第に彼女たちは心を開くようになる。治療者や看護者に対して表面的に取りつくろっていた患者が、ときには従順なまでの素直さを垣間見せる。ときには退行が進み、特定の看護者を独占しようとしたり、逆に反発して悪態をついたりするようになる。これが甘えをめぐる問題である。彼女たちは、抱えられた環境の中で、子ども返りをし、昔できなかった依存と攻撃という甘えの原点を繰り返しなぞるのである。そうやって、彼女たちは育ち直しをしていく。身体を張った仰々しい訴えではなく、少し控えめな、しかし実感のこもった(当たり前の)気持を口にするようになる。
このように、治療スタッフの役割は、抱える環境を提供し、「治りたい自分」のサポーターとなって、その成長を見守ることである。また、治ってしまうと家族が離れていくという不安をもちやすいので、家族や周囲に働きかけて、変わらぬサポーターでありつづけることを保証してもらう。さらに付け加えると、「治りたくない自分」が過去の傷に基づくものであるとすれば、それを捨て去ることへのつらさや寂しさに共感しつつ、「治りたくない自分」の後姿をともに見送る役目もある。
参考文献
1)下坂幸三. 摂食障害の治療指針. 摂食障害治療のこつ. 金剛出版;2001. p.9-14.
2)下坂幸三. 摂食障害―その現象と対策―. 摂食障害治療のこつ. 金剛出版;2001.p.30-49.
思春期における食行動の異常といえば、拒食と過食である。例えば、ダイエットややけ食いの延長上で、そうした状態が定着すると、摂食障害(Eating disorder)と呼ばれる病態となる。むろん、ダイエットだけが原因ではなく、その理由や背景はさまざまである。現代のようにダイエットブームではない19世紀にも「摂食障害」の症例は存在したのである。この障害は、米国精神医学会の精神疾患の診断統計マニュアル(DSM-Ⅳ-TR)では、表1に示したように3つ(下位分類を含めると5つ)に分類されている。臨床的に重要なのは、拒食症(無食欲症)と過食症(大食症)である。筆者が精神科医となった1980年代半ばには、拒食症と過食症の割合は拮抗していたが、近年では圧倒的に過食症の割合が増加(拒食症の約2倍)した。また、患者数は最近の20年間で約10倍に増加したともいわれ、社会問題化してきている。男子は少なく(5%以下)、診療に訪れるのはほとんど女子である。
表1 摂食障害の分類(DSM-Ⅳ-TR)
1.神経性無食欲症(Anorexia nervosa)
1)制限型(Restricting type)
2)むちゃ喰い/排出型(Binge eating/Purging type)
2.神経性大食症(Bulimia nervosa)
1)排出型(Purging type)
2)非排出型(Non-purging type)
3.特定不能の摂食障害(Eating disorder not otherwise specified)
拒食症は、標準体重の85%以下のやせがつづいて、無月経が起こってくる。心労などによる食欲不振とは異なり、いくつかの病的な特徴が認められる。約半数の患者がダイエットをきっかけにやせていくが、目標体重を過ぎても、体重をさらに減らすことにこだわりつづける(やせ願望)。自分のやせを認めようとはせず(否認)、むしろ太っているとさえ考えている(身体イメージの歪み)。ダイエットの有無にかかわらず、体重増加を極端に怖がり(肥満恐怖)、食事そのものを嫌悪するようになる。その一方で、飢餓の反動により、料理や食物に強い関心を向け執着するといった矛盾がみられる。また、やせているにもかかわらず、何かしていないと落ち着かない様子で勉強や運動に熱中する(過活動)。しかし、長続きせず徐々に対人関係が疎遠となり、活動は停滞する。表1に挙げたように拒食症には、少食によってやせを維持する制限型と、飢餓の反動で過食するようになり、やせを維持するために排出行動(1)を行うむちゃ食い/排出型がある。
過食症は、短時間に大量の食物を衝動的に食べる発作を繰り返す病態である。いったんむちゃ喰いがはじまると、自分の抑制が利かず食べることが止められない。何千キロカロリーもの食品を、しかも日頃は敬遠しがちな甘く脂っこい食品を短時間で食べ尽くしてしまう。過食後は後悔や自責の念にさいなまれ、居たたまれない気分に陥る。ここで排出行動をとるか否かで排出型と非排出型に分けられる。体重は標準体重の85%以上である。
拒食と過食は一見まったく反対方向の行動と映るが、時期によって拒食から過食へ(あるいは逆へ)変化したり、また制限型からむちゃ喰い/排出型へ移行したりすることが多い。また、やせ願望や太ることへの異常なまでの恐怖心が共通して根底にあり、片や空腹感が分からず、片や満腹感が分からずという、食をめぐって表裏一体の関係にある。
(1).自己誘発性の嘔吐または下剤、利尿剤や浣腸の乱用によって、内容物を速やかに体外に排出しようとする行動。英語では‘purging’といい、浄化・浄罪を意味するとともに、下剤をかけるという意味がある。
2. 摂食障害における心身の特徴
1)身体的な特徴
摂食障害によって生じることの多い身体症状を表2に掲げた。拒食症の身体症状は栄養失調に基づくものである。体重減少が進むと、脱水や電解質異常が生じ、不整脈が出現しやすくなる。さらに進むと、腎機能低下や心機能低下をきたし、死に至ることもある。これらの症状は体重が戻るとともに改善を示すが、成長期に栄養不良がつづいた場合、低身長となることがある。過食症の場合、体重が正常範囲にあり栄養状態に問題がないため、異常を認めないことが多い。しかし、排出行動が長期にわたると、電解質が失われ、体液のバランスを崩したり、腎機能や心機能の低下をきたすことがある。また、過食・嘔吐が続くケースでは、拒食症の場合でも、唾液腺(耳下腺・顎下腺)の腫脹、歯牙酸蝕症(2)、齲歯、吐きダコ(3)がみられる。骨の輪郭が浮き出るほどのやせでも、唾液腺の腫脹によってエラが張った特有の顔貌を呈する。
(2).歯のエナメル質表面の脱灰症。通常はメッキ工場などの酸性蒸気を吸う職場環境などで働く人の職業病として認識されているが、摂食障害者の場合、頻繁な嘔吐によって逆流した胃酸が歯牙を溶かす。
(3).のどに指を入れて吐くため、歯の当たる右手背の第1指、第2指の付け根に胼胝が認められることが多い。
表2 摂食障害による身体症状
拒食症
身体所見:低血圧、徐脈、冷え性、低体温、皮膚の乾燥、うぶ毛の増加
便秘、浮腫、カロチン症(皮膚の黄染)、抜け毛等
血液検査所見:肝機能障害、白血球減少、貧血、コレステロール値異常
電解質異常(低ナトリウム、低カリウム血症)など
内分泌異常:無月経(女性ホルモン低下)、低身長(成長ホルモン低下)
重篤な障害:低血糖性昏睡、脱水、腎不全、不整脈、心不全、骨粗鬆症、結核の合併など
過食症
身体所見:唾液腺の腫脹、歯牙酸蝕症、齲歯、吐きダコなど
血液検査所見:電解質異常、腎機能障害など
2)心理的な特徴
先に述べたように、拒食と過食は表裏一体の関係にあるので、合わせて述べるのが適切と思われるが、ここでは理解しやすいように両者を分けて述べることにする。
a)拒食の意味と利点
摂食障害は、まず拒食からはじまると考えてよい。20年以上前には、胃の調子が悪いとか、食べると気持悪くなるといった理由で無食欲(anorexia)を訴える患者が多かった。実はこの形が拒食症の古典的な原型である。今日ではあまり見かけなくなり、わずかに小学生までの発症ケースでみられる。このタイプでは、「成熟に対する拒否」(4)、「幼児期へのあこがれ」といった心理機制が指摘されている。
今日多いのは、前述したようにダイエットをきっかけに拒食に至るケースである。減量をめざした理由を患者に尋ねると、体形について知人や級友から何か指摘されたとか、美しくなりたい、俊敏になりたいとかいった答えが返ってくる。これらはいずれも他者の評価を意識するものであり、自分の存在感を集団の中で、また自分自身の中で高めたいという願いにほかならない。彼女らはなにゆえに自己存在感を求めるのか。拒食に向かう背景として、挫折や敗北体験が挙げられる。勉強、部活動、友人関係などで自分の優位性を保てないと感じる体験を経て、拒食に至る。彼女たちは元来強迫的で、完全主義的な性格の持ち主であるとともに、自己愛的な高い達成欲求をもつ人々である。そのような人間にとって、挫折や敗北は耐えがたい体験である。下坂1)は、拒食の意味を「自己存在の証し」と指摘し、「挫折体験を希薄化させると同時に、自己をコントロールすることができるという力感・達成感と身体的な存在感覚の強化とに裏打ちされた『かりそめの自分らしさ』の樹立」であると述べている。彼女たちは、絶えず食品のカロリーをチェックし、日に何度も体重計に乗り、鏡でやせ具合を確認する。食べると太るという強い信念(肥満恐怖)があり、飢餓感を押さえこみ、自己を統制することに全身全霊を傾けている。身体を賭けた自己存在の証明である。やせを達成していく自分に自己存在感を感じて、自己愛的な満足を得ているのである。彼女たちの自己愛は、人並みであることを嫌悪し、人とは違っていたいという心性(「平凡恐怖」2))にも反映している。度を超したやせという現実を受け入れず、躁的防衛(5)で「大丈夫」と言い張り、過剰適応的に行動する。また、拒食をめぐって家族の関心を一身に集め、家族の中で確実に存在感が増大してくる。やせ衰えた身体の持主ということで役割や責任が大幅に免除され、手厚く配慮されることになる。家族を巻き込み、親を思い通りに操ることができるのである。こうした意味や利点を持つ症状を彼女たちは簡単に手放すことはできない。
(4).体の成熟や女性性を嫌悪したり拒否したりする心性をさすが、フェニミズムの文脈では、摂食障害を女らしさの文化規定から逃れて、女性が自分自身の自律性を保つための行為と規定している。
(5). 抑うつ的不安,罪悪感,そして喪失感から自我を保護するために、その現実を否認し、現実を万能的に解釈しようとする心的機制。
事例A 中学生女子 13歳
A子は幼児期よりしっかりしていて、手のかからない子であった。小学校では教師から色々な場面で模範的であると評価されていた。中学に入学し、バスケットボール部に入部した。少しぽっちゃりした体形であったが、部活の上級生から「もう少しすばやく動けない?」と注意されたのをきっかけにA子はダイエットを決心した。みるみる体重は減ったが、イライラして怒りっぽくなった。母親の作る食事に難癖をつけ、調理方法に口出しするようになった。また、自分の食事(ご飯2口に野菜の煮物少々)を秤にかけて重さを測り、その数値を母親に確認させたり、母親や弟の食事に口をはさみ、あれとこれを食べろと指示したりするようになった。標準体重の-25%程度になっても、部活の早朝練習に率先して参加したり、学習塾へも積極的に通った。両親に説得される形で、やっとのことでクリニックを受診した。A子は最初困ることはないと言い切った。身体について聞いていくと、ガリガリの体を指して下腹と太股がまだ太いと述べた。そのうち、太ることがこわいと語り、次第に少し疲れやすいと告白した。
この後、A子は回復に向かっていくが、その過程で、「やせていたい自分」と「健康になりたい自分」が彼女の心の中で常に闘っていた。最初は圧倒的にやせを求める自分が大きかったが、徐々に健康を求める自分が育っていった。A子はしばしば回復の不安を語り、抑うつ的となった。回復すると、みんなが離れてしまう、見捨てられてしまうといった自立をめぐる不安である。回復してもなお家族や治療スタッフから支援されるということが信じられるようになると、健康を求める自分が大きくなっていった。
b)過食の意味と利点
過食は、拒食の挫折であり、拒食で押さえこんでいた飢餓感の猛烈な解放である。食べることの自己コントロールを手放したが、自分の中にあふれる不安や緊張を刹那的に過食が緩和してくれることを知るのである。また、強い肥満恐怖に応えるように、自己誘発性の嘔吐や下剤の乱用が過食による体重増加を抑制し、拒食の代替となって機能するようになる。過食・嘔吐や下剤の乱用は、口腔から咽頭、食道、胃、大腸、肛門に至る身体感覚を増大させ、自己存在感を高めるのである。すなわち、過食もまた、拒食と同様に、身体を賭けた自己存在の証明という意味がある。さらに、過食から嘔吐に至る一連の行為が強烈なストレス解消法であるとともに、麻薬のような密やかな快楽となっているのである。
事例B子 高校生女子 17歳
B子は元来負けず嫌いで、勝ち気な性格であった。女子高に入学後、ダイエットをきっかけに拒食となったが、すぐに過食に転じた。毎夜、夕食を普通に食べた後、余っているご飯やおかずを平らげ、さらに冷凍庫のピザやグラタンを温めて食べ、最後に学校帰りに買っておいた菓子パンを何個か詰めこむのである。B子は、食べている間は無心になれる、何も考えなくていいしホッとできると言う。しかし、いよいよ食べ尽くす頃になると、やるせない気分がみるみる胸いっぱいにこみあげてくる。急いで、B子は風呂に入る。彼女の場合、風呂場のシャワーで音を消して、思う存分ビニールのゴミ袋に吐き出すのである。トイレでは家族に怪しまれるし、またどれだけ吐けたのか確認がしにくいと言うのである。思った通りに吐けたときにはスッキリするし、「よし!」という気になるのだと言う。じつは、B子は授業中に、夜の過食に備えて何を帰りに買っていこうかとウキウキした気分で思い描いていると告白した。しかし、B子は急にどうにも切ない気分が襲ってきて、何もかもが嫌になって死にたくなることがあるとも語った。
このように、過食・嘔吐には秘事を愉しむ気配が強い。これは性的なニュアンスを含むものであり、口腔を通した自慰行為と捉える見方もある。一方で、先に述べたように、過食が拒食を貫き通そうとした意思の挫折であるため、抑うつ感や絶望感をもつことが多い。拒食では徹底されていた自己規律(強迫のしばり)が保てなくなり、心のあちこちにゆるみの出た状態である。そのため、衝動の抑制が利かず、自傷行為や大量服薬といった行動化や性的な行動化をしばしば認める。
さて、B子の場合も治療経過の中で、「治りたい自分」と「治りたくない自分」が心の中にあることが明らかとなった。治りたくない自分は圧倒的に大きく、刺激的なストレス解消法を失いたくないし、密やかな快楽を捨て去れないと言うのである。一方、治りたい自分は最初のうち観念的で頼りない存在であった。治りたい自分が日常の何げない問題に向き合って処理できたりするようになるにつれ、わずかずつ存在感を増していった。長い治療経過の中で、紆余曲折を経ながら、治りたい自分が自信をつけてふくらみ、B子の過食・嘔吐の回数は減りつづけて、人間関係の大幅な改善がみられた。
3.看護の役割
摂食障害の者たちは、これまで述べてきたように、家族の中であるいは学校の中で、身体を賭けて自己存在感を強く求めている人たちである。裏を返すと、摂食障害を発症するまでの間に、自分という存在に確かな手応えを感じていなかったということになる。こんなふうな自分を、家族や友人たち、まわりの人間が抱えてくれていて、それでいいよと保証してくれているといった安心感がないのである。彼女たちは、人を信じることができず、甘えることの下手な人たちである。治療に関わる際には、この甘えをめぐる問題が生じてくることに留意しておく必要がある。もう一つの留意点は、彼女たちの心の中に、「治りたい自分」と「治りたくない自分」が存在しているということである。治したいと宣言して入院したものの、病棟内でやることは治りたくないような行動ばかりという事態が往々にして起こる。そのとき、問題行動ばかりに目を向けて対応すると理解し合える機会を失ってしまう。彼女たちは人を信じられないが、心の底では人を信じたいのである。誰にも分かりっこないと思いながら、分かってほしいのである。治りたいが、治りたくないという矛盾した気持をその都度汲みながら寄り添っていくと、次第に彼女たちは心を開くようになる。治療者や看護者に対して表面的に取りつくろっていた患者が、ときには従順なまでの素直さを垣間見せる。ときには退行が進み、特定の看護者を独占しようとしたり、逆に反発して悪態をついたりするようになる。これが甘えをめぐる問題である。彼女たちは、抱えられた環境の中で、子ども返りをし、昔できなかった依存と攻撃という甘えの原点を繰り返しなぞるのである。そうやって、彼女たちは育ち直しをしていく。身体を張った仰々しい訴えではなく、少し控えめな、しかし実感のこもった(当たり前の)気持を口にするようになる。
このように、治療スタッフの役割は、抱える環境を提供し、「治りたい自分」のサポーターとなって、その成長を見守ることである。また、治ってしまうと家族が離れていくという不安をもちやすいので、家族や周囲に働きかけて、変わらぬサポーターでありつづけることを保証してもらう。さらに付け加えると、「治りたくない自分」が過去の傷に基づくものであるとすれば、それを捨て去ることへのつらさや寂しさに共感しつつ、「治りたくない自分」の後姿をともに見送る役目もある。
参考文献
1)下坂幸三. 摂食障害の治療指針. 摂食障害治療のこつ. 金剛出版;2001. p.9-14.
2)下坂幸三. 摂食障害―その現象と対策―. 摂食障害治療のこつ. 金剛出版;2001.p.30-49.